
解決事例
解決事例一覧
-
CASE 1
問題社員を解雇したい
入社して数カ月経つ社員について、何度教えても仕事が覚えられないから解雇したい!とご相談を受けました。
解決策
「問題社員を解雇したい!」というご相談は多いですが、解雇の判断は社員の人生を左右する大変な重責ですので、慎重に検討しなければいけないことを、まずお伝えします。
その上で、主に次のポイントを整理して解決に導いています。
1.対象社員に対して、教育改善指導(何が問題で、どうすればクリアできるのか)を適切に示しているか。
2.改善指導歴を客観的に記録しているか。
3.試用期間中であるのか。試用期間の規定があるか。試用期間中の解雇事由に該当しているか。
4.解雇に関する規定があるか。解雇事由に該当しているか。
今回の事案では、試用期間の規定はあり、試用期間中でしたが、教育改善指導が不十分であったため、まずは再度改善するべきことと、改善対応の期限を明確に伝え、対象社員への指導記録を残すことを助言しました。
結果、やはり仕事のミスを繰り返し、改善の見込みがないと会社は判断し、対象者本人も自分の能力不足を認めて、円満に雇用契約を終了することとなりました。
また、会社に対しては、就業規則の試用期間中の解雇に関する事由が不明瞭であったため、就業規則の改定を助言し、当オフィスで改定と届出を実施し、今後のトラブルにむけた予防も強化できました。 -
CASE 2
慶弔休暇を今さら申請してきたのですが?
就業規則の特別休暇(慶弔休暇)として、「父母が死亡したときに5日」と規定されている会社様からのご相談でした。
ある社員が退職するときに「2年前に父親が亡くなったときの慶弔休暇を申請しなかったので、退職前に有給休暇消化と合わせて慶弔休暇5日の取得を申請する」と言われたのですが、認めないといけないのでしょうか?とご相談を受けました。解決策
慶弔休暇は、その対象事実が生じたときに、会社が社員への福利厚生の目的で認めて付与するものです。
その休暇は、その対象事実に対して客観的に適切な時期に申請をして会社が認める場合に取得ができると考えるのが筋ではありますが、法的な決まりはありません。
就業規則に取得期日の記載が無いと、このようなケースが生じる可能性があるため、取得のルールを明確に記載することが重要です。
この事例では、上記のような助言を会社担当者に対して行い、会社が対象社員に慶弔休暇の本来の目的と、会社は申請を認めないことを説明し、対象社員も渋々同意して解決しましたが、速やかに会社の就業規則改定のご依頼を頂き、対応いたしました。
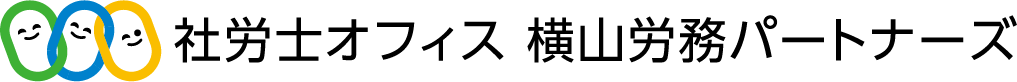
 TOP
TOP



